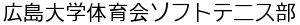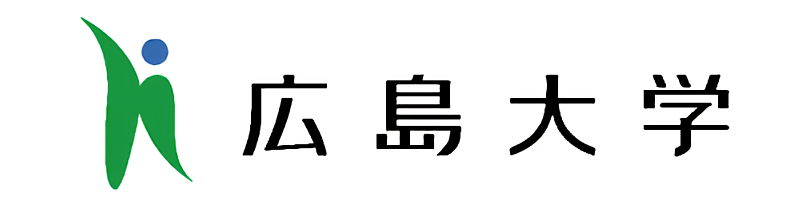児玉 惇(昭和33年卒)
テニスコートが縁遠くなってすでに随分になり、テニスはもう思い出の中に沈んでいる。
私と軟式テニスとの付き合いは、小学校6年生だった昭和22年の夏休みに、父親とのボール遊びから始まった。振り返れば、これは大きな意味を持っていた。
この年は新制中学のスタートの年だが、どの学校も校舎すらままならぬ状態で、まだ混沌の中にあってクラブ活動どころではない実状にあった。翌23年、旧制中学は新制高校に移行して、戦時中中断していた運動部の活動も復活した。庭球もその中にあった。
この年、私は中学生になった。師範学校に残っていた荒れたコートでの私の庭球は練習らしくなっていった。まだほとんどの新制中学で練習らしい練習をしていなかったから、当然中学生の試合などない時代だった。
昭和26年、高校生になって、当然のように庭球部に入った。コートの少ない時代だったから、夕方になると一般の人も集まってきて、練習は日没まで続いた。同級生の部員は、私と同じ中学の出身者を除けば、高校に入って初めてラケットを握るという者がほとんどだった。
1年の秋、市内大会で決勝まで進んだ。相手は同じ高校のキャプテン、旧制中学の最後の入学生で、大変な貫禄だった。「1年生がよくここまで来た。おまえ達の優勝だ。」と、試合をしてもらえなかった。2年の春、県大会で優勝した。同年代としてはテニスのキャリアに少々差があったからであろう。3年の夏には全国の優勝が転がり込んだ。私どもにも年ごとの成長はあったのだろうが、相手が自分の得意技を自ら封じてしまうという幸運に恵まれた故であった。
昭和29年、大学では硬式に転向して楽しもうと思いながら、誘われるままに軟式を続けることになってしまった。私のテニスはテンポの早さが特徴だった。フォアもバックも、可能な限り胸から肩口の高さのボールを叩いていた。ボール自体の速さはそれほどでもないのだが、テンポは早かった。それはある種の効果(攻撃力・破壊力)をもっていた。
そこに私の勘違いが生じた。私は、勝利のために更なる破壊力を速さに求めた。速いボールを打とうとした。それもテンポの早さではなく、ボール自体の速さを求めた。ところが、ボールのスピードには限界がある。自分の実力以上にスピードを上げれば、途端にミスが増加して、ゲームは自滅となる。私は実力を上げるだけの練習量を確保できなかったから、私のゲーム運びは乱暴なものになっていった。ひどく派手なゲームは、安定した結果をもたらさなかった。それでも、在学中そこそこの戦績であったのはパートナーに人を得たからに他ならないのだが、それだけに、申し訳ない気持ちは今に至るまで消えない。
大学卒業後は、私自身が試合にでることは殆どなかったし、そのための練習もしなかった。ただ、生徒のインターハイ出場のために、毎日コートに出て、生徒相手にラケットを振り続けた。それも10年足らずで終わって、軟式テニスとの縁は切れてしまった。
縁は切れたが、私の人生観も処世術も、基本はそれぞれのテニスコートで形作ったものだ。その意味で、私はいまだにどっぷりとテニスに浸かっているとも言える。それは、悪い気分では毛頭ない。